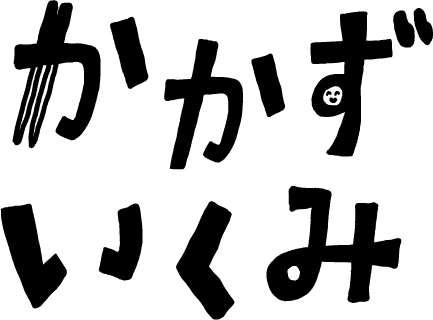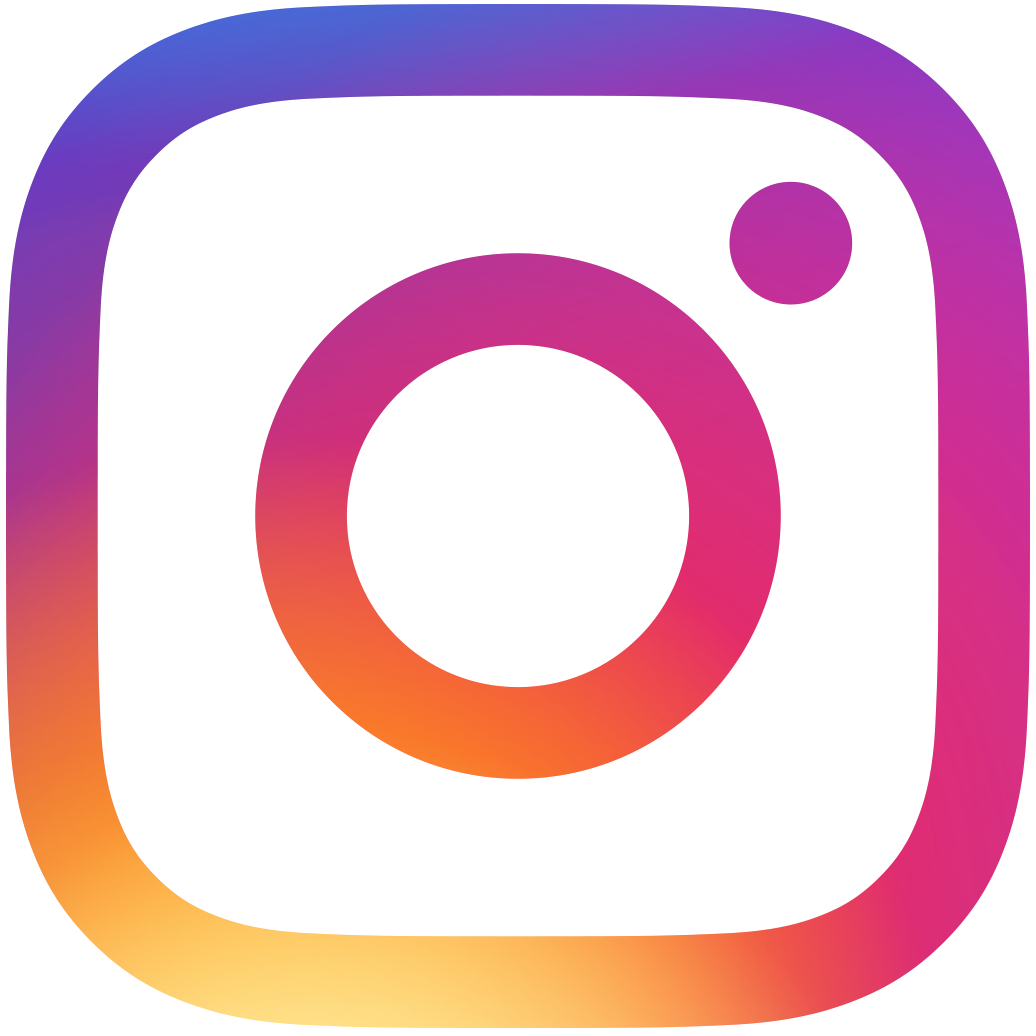- HOME
- 取り組み
取り組み
糸満市議としての活動報告
学校給食
学校給食の地産率の向上はもちろんですが現在の地産率は約2割を推移しており農業従事者の多い糸満市の第一次産業がまだまだ活かされていません。しっかりとテコ入れを行い、地産率のアップと第一次産業従事者の所得向上に繋がる仕組みを作る提案をしてきました。
学校給食の地産率の向上はもちろんですが、議会では学校給食の牛乳を取り上げてきました。アレルギーではなくてもお腹が緩くなる(乳糖不耐症)ため、牛乳を飲めない生徒もいます。その場合、牛乳の停止手続きを学校で申請すれば牛乳分の給食費が減額してもらえます!
その額1食70円、月1400円給食費が安くなります。飲まずに破棄されてしまう牛乳にお金を支払い続けている方への周知も不十分と感じています。また牛乳だけで年間約16トンの食品ロスが出ている現状もあります。

熊野鉱山と辺野古新基地
米須にある熊野鉱山から石灰石を採掘する申請がなされた(所有会社から)ことから、沖縄戦の終焉地であった南部から土砂が採掘され、辺野古新基地建設の埋め立てに使われる計画になっています。現段階で業者からは遺骨混じりの可能性のある表土をどかし、石灰石を採掘し、表土は元に戻すため、遺骨が混じることはないとしているが、南部地区の土砂には戦没者の血が染み込み今も遺骨が残っている。そのような土砂を米軍基地建設のために埋め立てるのは戦没者に対する冒涜である。またトラックの搬入出のルートの真下にある遺跡は米須自治会からも保全を求める声もある。議会でも長い時間をかけて取り組んできた課題の1つです。

コロナワクチン事業
私は新しいワクチン事業に関して、とても慎重に考えています。治験データを読み解き有効性安全性を判断することは、医師であっても意見の別れる難しい問題です。
大切なのは、本人がしっかり納得した上で判断することだと考えます。そのために、判断材料となるデータをできる限りわかりやすく開示し、有効性だけではなくリスクをしっかり踏まえ、医師から説明を聞き、その上で判断するべきです 。
また、コロナワクチンは早急に沢山の人に接種することが急務とされ、本来筋肉注射をする場合には逆血確認(刺した針が血管に当たっていないか確認する行為)が必須ですが、コロナワクチンは逆血確認が不要となりました(国が正式に医療機関に通知)。
多くの人がこの事実を知らされることなく、早く沢山の人に打つことが優先された集団接種となり、安全性が置き去りにされていると感じるのは私だけでしょうか?
またワクチンでの健康被害を証明することは難しく、因果関係は不明となることが大半です。2021年7月以降、国から安全性と有効性のデータは開示されていない現状もあり、医療法1条第4の2項(説明と同意)が行使されていない事実もあり、議会でも追及をしてきました。

農業
生きる基盤である食。第一次産業(農業、漁業)なくして生きていくことはできません。
今は外から沢山の食材が安く入ってきますが、有事の際にも地元で食べ物が確保できるかがとても重要になると考えます 。能登の震災でも、道路が寸断され物資がなかなか入って来ない状況となり、その際、市民を飢えから守ったのは地域に沢山ある畑だったそうです。
糸満にも沢山の農家さんがいますが、学校給食での糸満産食材の使用は約20%にとどまっており、積極的に使うことで地域内で回る経済を作り、農家さんが安心して働けるように安定収入への取り組み、そして後継者育成につながる環境作り、何よりも安全安心な食を子ども達に食べてもらい身体的な健康と経済的な健康を求めて参りました。そして、元々の糸満の文化であった稲作の復活。
実は糸満でも戦前はお米を作っていた歴史があり、糸満の各地に残る綱引きがその証です。
田んぼでとれた稲藁で綱を編み豊作を祈願し、綱引きを行ってきた。また土壌が元気であれば海へ流れる養分も豊富となり、海の健全な環境にも寄与し、大漁にもつながると云われています。

福祉
糸満市障がい者等日常生活用具の給付に関する要綱が平成23年に基準額が定められましたが、これまで約13年間一度も改定がされていません。ストーマ装具を使用するオストミー協会から基準額に係る見直しを求める要請書も提出されています。物価高騰がある中、食材や電気代だけではなく、障がい者の方々の生活用品も、値段が上がり家計に重くのしかかっています。早急に改定が求められます。また、一時ストーマ(簡易ストーマ)を使用されている方は身障手帳を取得できない為、給付の対象外となっています。そちらに関しても県や国に対しても改善を求めていきます。

国に対しての意見書・決議提案
- 2022年3月議会にて
-
新型コロナウィルス感染症に係るすべての差別や偏見等の根絶に関する決議
-
昨年2月より新型コロナワクチン接種が始まり、同ワクチンの接種・非接種による人権問題が顕著化している。市民一人一人の参加によって人権が尊重され、住みたい、住み続けたいと感じられるまちの実現を図るために、同感染症に関する様々な人権問題に取り組まなければならない。
本市の基本構想では、「子どもの人権を守り、子どもも親も安心して過ごせるまち。」、「人権を尊重し、多様な生き方を認め合う共生のまち。」を目指しており、住みやすいまち糸満市の実現に向けて、同感染症に係る全ての差別や偏見、誹謗中傷等の根絶を目指し、以下の事項について決議する。
- 新型コロナウイルス感染症の感染者及びその家族に対する不当な差別・偏見・誹謗中傷をさせない。
- 医療や介護、保育などの現場で社会を支えている人たちとその家族に対して敬意を払い、不当な差別・偏見・誹謗中傷をさせない。
- ワクチン接種・非接種による不当な差別・偏見・誹謗中傷をさせない。
- 新型コロナウイルス感染症に関する正しい理解を広げ、市民一丸となって人権侵害の防止に努める。
令和4年3月22日
糸満市議会
-
- 2022年6月議会にて
-
新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意見書
-
厚生労働省は、令和3年2月(2021年)より予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種に用いることとなったワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)接種により発症予防、重症化予防に新型コロナワクチンの接種が有効であるとされ、新型コロナワクチンの接種が実施されてきた。
その後、新型コロナワクチン接種後に因果関係が疑われる持続的な疼痛が特異的に見られている。令和4年6月10日、厚生労働省の第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会においては、令和4年5月15日時点の重篤副反応者数7,287名、死亡者数1,726名についていまだ因果関係は解明されず、救済体制はほとんど進んでいない現状があります。
その間にも、接種後の副反応の症状に苦しむ方々が全国で声を上げています。同年3月24日「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について」において厚生労働省から各県に専門的な協力機関を設けること、医療機関からの副反応報告が確実に行われること等が報告されているが、これまでの新型コロナワクチン接種後の副反応被害について、国の責任において調査し実態把握すること、原因解明を急ぐとともに、新型コロナワクチン接種後に日常生活に支障が生じている方々に対して医療支援を実施することが急務である。
よって、国において国民の健康と安全のため、下記の事項を実施するよう強く求める。
記
- 新型コロナワクチンによる副反応、後遺症に関し因果関係の解明を急ぐとともに、国民に対し速やかに情報提供を行うこと。
- 新型コロナワクチンを接種した方に対し、接種後の被害実態調査を実施し、公表すること。
- 医療機関に働きかけて接種後の副反応、後遺症被害への治療法の確立を急ぐこと。
- 新型コロナワクチンの接種後に日常生活に支障が生じた方々への補償、並びに相談事業の拡充と各地域の医療機関の連携による対応を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和4年6月27日
糸満市議会
-
- 2022年9月議会にて
-
児童福祉としての保育制度の拡充を求める意見書
-
令和元年10月より、3歳から5歳までの全ての子供及び住民税非課税世帯のゼロ歳から2歳までの子供を対象とした幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料を無償とする幼児教育・保育の無償化の実施がされてきました。
しかしながら3歳未満の児童については住民税非課税世帯以外は無償化の対象となっておりません。そこで児童福祉における公平性の観点から国及び政府に対し、幼児教育・保育の無償化を持続可能なものとするために、幼児教育・保育の無償化を国費で全額負担とする制度を強く求めます。
急速な少子化が進む中、児童福祉としての保育事業の質の向上と安心して子供を産み育てることができる社会の実現が強く求められており、子供の健やかな成長を支えるためには、質の高い保育サービスの提供と保育の担い手の確保が重要です。
子供の安心・安全な保育を保障すると同時に子育て家庭の支援を強力に行い、保育士の配置基準を見直し、実態に見合った給与の実現、保育士・調理員の配置基準の抜本的改善が急務です。また、公立保育所や認可保育園へ入所できない児童は認可外保育園に頼らざるを得ない状況が続いているが、行政による援助が著しく少ないため施設の整備拡充が極めて困難な状況であり早急な対策が求められます。
よって、国において児童福祉の安心・安全のため、下記の事項を実施するよう強く求めます。
記
- 少子化対策推進のため3歳未満の児童について保育費完全無償化の実現。
- 保育所等の早急な職員配置基準の見直しや公定価格の引上げなど、保育士等職員の処遇を改善するための必要な支援のさらなる周知を行うこと。
- 認可外保育園に対する支援について、特別措置として具体的な支援策や財政措置の取組を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和4年9月28日
糸満市議会
-
- 2023年9月議会にて
-
トリガ一条項凍結意見書
-
現在全国でガソリン価格が高騰している。政府はガソリン価格の上昇抑制策を継続する一方、ガソリン税の一部を軽減する「トリガー条項」の発動は見送る方針を固めた。
8月に行われた毎日新聞の世論調査では物価高が生活に「影響」しているとした回答が92%、負担軽減策の延長が「必要」だとした回答が83%と国民の意識も軽減策に注視をしていると言える。
また沖縄においては公共インフラが本土に比べ整っておらず、ほとんどの世帯で移動手段は「自動車」となっており燃料費高騰が家計に重くのしかかっている。訪問介護やデイサービスの送迎においても自動車が利用されており、燃料費高騰は市民生活やあらゆる職種の事業経営に影響を与えている。また沖縄の所得格差の問題やひとり親世帯の貧困等に鑑みても早急に措置が必要である。
現在、運用が凍結されているトリガー条項の凍結解除を早期に行うことを求めると同時に、地方税の減収分は国の予算措置によって補填するとともに重油、灯油についても効果的な価格安定策を講じることを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月26日
糸満市議会
-
- 2023年12月議会にて
-
パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める意見書
-
世界保健機関(WHO)では、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて将来の感染症の蔓延に備えるため、WHOの憲章第21条に基づく国際保健規則(IHR)を改正するとともに「パンデミックの予防、備え、対応に関するWHO条約、協定その他の国際文書」(パンデミック条約)を新しく制定する協議が2021年12月のWHO総会以降の政府間交渉会議(INB)において、同時並行で進められている。2024年5月のWHO総会には、パンデミック条約の草案及び国際保健規則改正案の提出が予定されている。
現在、WHOのウェブサイト等で公開されている英文等の草案及び改正案では「加盟国がWHOの勧告に従うことをあらかじめ約束し、WHOの勧告に法的拘束力を持たせる」、「WHOの国際的なワクチン配分計画を作成し、加盟国がこれに基づくワクチンの製造や供給を行う」、「ワクチン等の健康製品の迅速な普及のため先進国は、途上国に対する経済的、技術的及び人的な提供等の援助義務を課せられる」、以上の内容が含まれており、加盟国の政府の判断がWHOの勧告に拘束され、保健政策に関する国家主権の侵害となり、基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念される。しかし、日本ではこれらの草案の内容や交渉過程が国民に周知されているとは言い難い状況にある。
よって、国においては下記の事項を実施するよう強く要請する。
記
- 現在、WHO総会で行われているパンデミック条約の草案及び国際保健規則改正案に関する協議内容や国民生活への影響等を分かりやすく国民に周知すること。
- 議員、有識者、その他の国民から意見を聴取する手続を早期に開始すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月22日
糸満市議会
-
- 2024年3月議会にて
-
地方自治法改正に関する意見書
-
政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を閣議決定し、法案を国会に提出した。
日本弁護士連合会は、本年1月18日付けで「第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」における大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書」(以下「意見書」という。)を公表し、答申に基づく法案の国会提出に反対した。
意見書では、答申の「第4」で示された「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設は、2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題があることを指摘した。
すなわち、答申の「第4」は、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍についての実証的な分析検証が行われていない点、法定受託事務と自治事務を区別せずに国の指示権を論じている点、及び現行法では国の地方公共団体への「指示」は、個別法で「緊急性」を要件として認められているのに対し、一般法たる地方自治法を改正して、自治事務についても、個別法の根拠規定なしに、かつ「緊急性」の要件も外して、曖昧な要件のもとに国の指示権を一般的に認めようとする点で、地方分権の趣旨や憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題があるものである。
しかし、今回出された法案は、これらの問題点を解消するものとは到底言えない。
すなわち、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍については、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに地方自治法を改正する必要性があるのかが疑問であり、その点が法案提出に際して、十分に検討された形跡はない。また、法案は、現行法の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設けて特例を規定するとして、この点において法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってしまっている。さらに、法案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」、「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外してしまっており、濫用が懸念される。そして、2000年地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。
以上の事から、国においては、下記の事項を実施するよう強く要請する。
記
- 「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例」に関する章のうち、「事務処理の調整の指示」を定めた第252条の26の4における「指示」を「要求」に改めること。
- 「生命等の保護の措置に関する指示」を定めた第252条の26の5を削除すること。
- 「都道府県による応援の要求及び指示」に関する第252条の26の7の標題を「都道府県による応援の要求」に改めた上で、同条第2項以下を削除すること、及び第252条の26の8の標題を「国による応援の要求」に改めるとともに、各大臣の指示権を規定する同条第4項以下を削除することを求める。
令和6年3月
糸満市議会
-
- 2024年3月議会にて
-
食料・農業・農村基本法改正に伴い基本法に「種子の自給」を盛り込むことを求める意見書
-
コロナ禍以降、世界各地の紛争や気候変動、円安などにより、輸入頼みには大きなリスクがあることが明らかとなり、中でも食料の自給は多くの国民の関心事となっている。 特に種子は農業にとって基本的で不可欠の要素であり、その自給が危うければ、食料の自給も万全とは言えない。一方、これまで公的に守られてきた種子の自給、つまり各地方の試験場と採種農家が連携しその土地の気候や風土にあった優良な種子を生産してきた技術は担い手の高齢化等で失わ れつつある。
地域の環境で生物多様性に沿う種子は一度失われたら取り戻すことは難しく、他の生産資材とは一線を画するものである。
よって、国におかれては第213回国会で審議される「食料・農業・農村基本法」改正において次の事項を実現されるよう強く要望する。
記
- 「食料・農業・農村基本法」改正に「種子の自給」を盛り込むこと
令和6年3月
糸満市議会
-
- 2024年4月臨時議会にて
-
パレスチナ自治区ガザ地区における再停戦を求める決議
-
現在イスラム抵抗運動(以下「ハマス」という。)のイスラエルに対する攻撃を直接的な契機として、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ地区に対する無差別爆撃と地上侵攻が続いている。こうした中、国連総会は昨年10月26、27日の2日間緊急特別会合を開き、人道目的での休戦を求める決議が採択された。同決議は、「即時、持続的な人道的休戦」を求め、イスラエルとハマスの双方をはじめ全ての当事者に対し、国際人道法の遵守と、ガザ地区への必要不可欠な物資とサービスの「継続的、十分かつ妨害のない」提供を求めている。また、捕虜となっている全ての民間人の「即時かつ無条件の解放」を求めるとともに、国際法にのっとった安全、福祉、人道的な処遇を要求している。
この間、双方の話し合いによって限定的な停戦で人質や捕虜の解放が行われた。戦闘休止で合意していたが、再延長に合意できず戦闘再開で、2024年4月17日の東京新聞の報道では「ガザ保健当局によると、ガザ側の死者は全体で3万3千人を超え、うち女性と子どもが約7割を占める」と報道した。
また、国連食糧農業機関(FAO)などが19日にまとめた報告書は、ガザ地区の人口の9割以上が、丸一日食料を入手できない状態に置かれている実態を明らかにしている。
戦闘の拡大でより多くの住民の命が危機にさらされる懸念が拡大している。沖縄はさきの大戦において一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦を経験したことから、我が国をはじめ、世界に向けて恒久平和を希求し発信してきた。多くの子供たちや住民が犠牲となっているガザ地区の状況は、凄惨な沖縄戦の記憶と重なり、多くの県民が心を痛めており終焉の地である糸満市から恒久平和を発信する意義は大きい。
よって、糸満市議会は、両者が国連決議を尊重し、ガザ地区での破局的な事態を回避するため、即時の人道的停戦に応じることを強く求め、全ての人質の即時かつ無条件の解放及び人道的支援の拡大を求めるものである。よって、本市議会は、これ以上人道危機が悪化しないよう国連総会決議に基づき早急な再停戦を求めるものである。
以上、決議する。
令和6年4月
糸満市議会
-